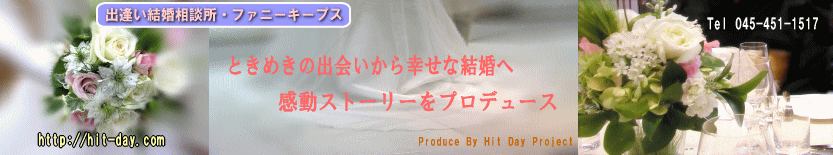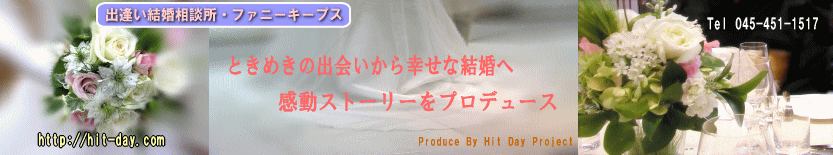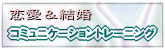■婚姻の成立
婚姻が成立するためには、民法上の条件が満たされていなければなりません。 |
男性は18歳、女性は16歳にならなければ結婚することができません。
婚姻適齢年齢に達していても、未成年の場合は父母の同意が必要です。
ただし、父親か母親のどちらか一方が反対していても、もう一方が賛成しているなら
結婚は可能です。
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすること はできません。(重婚の禁止)
女性が再婚する場合、前の婚姻の解消(離婚)から6ケ月経過していなければなり
ません。
再婚後妊娠したときに、前の夫の子か現在の夫 の子か判断できなくなるためです。
ただし、離婚前から妊娠がわかっていた場合や前の夫との再婚については、
この限りではありません。
直系血族(祖父母、父母、子、孫)や三親等以内の血族(曾祖父母、叔父母、兄弟、
甥姪)とは結婚できません。
しかし、四親等にあたる従兄弟とは結婚することができます。
|
■婚姻の効力
婚姻が成立すると、法律によっていくつかの 効果が発生します。 |
夫婦は、夫または妻、どちらか一方の姓に統一しなければなりません。
現在夫婦別姓は現行制度では、法律上の婚姻 とは認められず、内縁という形
になります。
なお、配偶者が 死亡したときは、婚姻前の姓に戻ることもできます。
未成年者が婚姻した時は、成年に達したものと見なされます。
これによって、親権や契約締結の能力を取得することになり、行使することが
できます。
夫婦間で交わした契約は、、第三者の権利を害さなければ、婚姻中なら
いつでも一方的に取り消すことができます。
「法律は家庭に入らず」が法律の原則だからです。
|
■夫婦の財産
夫婦の財産についての基本的な考え方です。 |
婚姻の届け出前に「夫婦財産契約」を結んでいない場合には、夫婦別財産制
になります。
夫婦別産制とは、「夫のものは夫のもの、妻のものは妻のもの」で、結婚前から
持っていた財産や自分たちの名義で得た収入は、全て名義人の財産であると
いう制度です。
その財産を夫婦共有の財産にするには、婚姻届を出す前に「夫婦財産契約」を
結んでおく必要があります。
婚姻届けを出した後で、その財産関係を変更することはできません。
しかし、夫婦には、相互扶助の義務があるので、日常生活の範囲内で必要な
ものは、夫婦共有財産として使われます。
夫婦財産契約をしていない夫婦の場合、日常生活においてどちらか一方が債務
を負ったときは、もう一方にも同じように返済の義務が生じます。
ギャンブルや贅沢品に注ぎ込んでできた借金や、経営に失敗して抱えた負債は、
日常生活の範囲ではないので、 連帯責任は問われません。
|
■相続
相続については厳密に法律で定められています。 |
婚姻が成立し、お互いが配偶者としての身分を取得したら、相互に相続関係が
成立します。つまり、相続人としての権利が発生するわけです。
配偶者は相続において、常に第一順位にあります。
たとえば、夫が死亡して子供がいないときは妻が全財産を相続し、子供がいる
場合は、妻が遺産の二分の一を、残りの二分の一を子供が相続し、夫の親族
には分配されません。
親と兄弟姉妹は、上の順位の相続人がいない場合のみ相続人となることが
できます。
配偶者と親が相続人になる場合は、配偶者が三分の二、親が三分の一を
相続します。
|